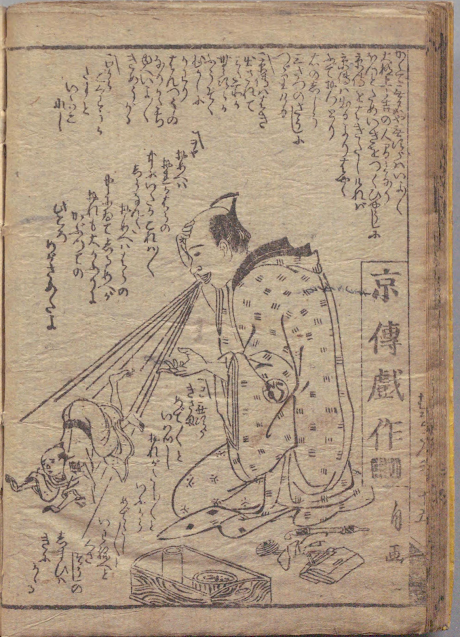P29 国立国会図書館蔵
(読み)
「ヲヤ
おや
於めへハ
おめえは
於連可者らの
おれがはらの
中 尓い多可これハ\/
なかにいたかこれはこれは
志ら奈ん多
しらなんだ
於めへハ者らの
おめえははらの
中 尓ゐて志るめへ可゛
なかにいてしるめえが
おれも大 可ふり尓
おれもおおかぶりに
かぶ川ての
かぶっての
此 ころ
このころ
め可゛さめ多よ
めが さめたよ
「コレ無次郎 可
これむじろうが
きさ満
きさま
めで\/と
めでめでと
いハ川し
いわっし
於れ可゛多し\/と
おれが たしたしと
いふ可ら
いうから
めで多し
めでたし
\/ と
めでたしと
い王袮へと
いわねえと
くさそうしの
くさそうしの
志まひハ
しまいは
き尓可ゝる
きにかかる
京 伝 戯作 ㊞ 自画
きょうでんげさく じが
(大意)
「おや、おめえへは、おれの腹の中にいたのか。これはこれはしらなんだ。おめえは腹の中にいてしるめえが、おれはしくじったもしくじった。このごろやっと目がさめたよ。
「これ無次郎、きさまめでめでと言え。おれはたしたしと言うから。めでたしめでたしと言わねえと草双紙はおわらねえんだ、気にかかるじゃねえか。
京伝戯作㊞ 自画
(補足)
「大可ふり尓かぶ川ての」、『おおかぶり おほ― 【大かぶり】
〔「かぶる」は芝居関係者の隠語「毛氈(もうせん)をかぶる」の略で,失策の意〕
大失敗。おおしくじり。「知れると―さ」〈洒落本・古契三娼〉』
変体仮名「女」(め)がたくさん出てきています。それらどれも「め」ではなく「女」のほうに近いようにみえます。
映画「ミクロの決死圏」では最後、涙と一緒に体から脱出したとおもいましたが、京伝、無次郎がため息で脱出とは幸せでありました。めでたしめでたし。おしまい。