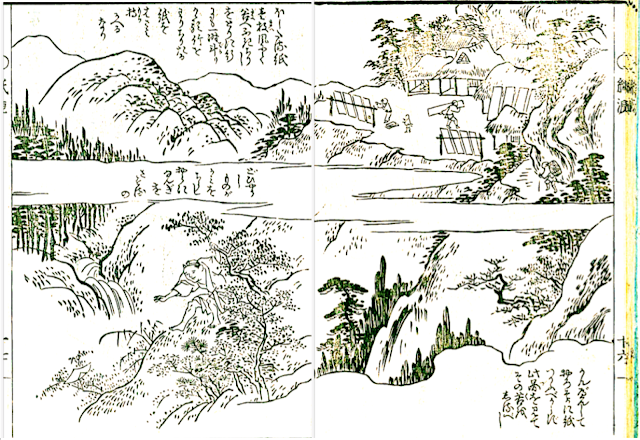P.38 石州高角 正一位人丸大明神社圖
(読み)
石 州 高 角 正 一 位人 丸 大 明 神 社 圖
せきしゅうたかつの しょういちいひとまるだいみょうじんじゃづ
吹 上 濱 湖水
ふきあげはま こすい
くまの松 高 津川 た可つの 長 門可い道
くまのまつ たかつがわ たかつの ながとかいどう
中 の嶋 社 家
なかのしま しゃけ
高 角 町 渡 し場
たかつのまち わたしば
(大意)
地図の地名等なので省略します。
(補足)
見出しの「高角」の「高」は「髙」(はしごだか)ですが、
「高津川」、「高角町」では「亠」+「る」のようになってます。
「中の嶋」、「嶋」のくずし字の山偏は「W」のような感じです。
「高角」の読み方が迷いますが、中段に「た可つの」とありました。
「長門可い道」、「道」のくずし字は特徴的です。
最後の地図絵図で、最初にあった「人麻呂の像」から、紙漉重宝記の締めを飾るにふさわしい「人丸大明神社」に戻ってきました。
この頁と次頁はつながっていて、絵師は紙一杯に絵筆をふるっています。
吹上浜の帆の上に広がる狭い空だけを余白として、描き込めるもの何でも、描き残しがないよう
悔いを残さず細かく細かく描いています。米粒のような人も町人・武士・荷を運ぶ人・旅人とわかります。
「くまの松」が大きく立派です。その前を流れる「高津川」は次頁の山間から流れ、蛇行して「吹上濱」の河口へと向かっています。
前頁の「濱出し」はこの「吹上濱」まで運んでいたのでしょう。
下部には民家が密集して賑わっている村であることがわかります。
川が賑わっている街のすぐ側を流れているのに橋がありません。
よく見ると一番下のところに「渡し場」がありました。